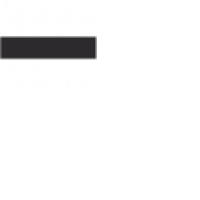皆さん、こんにちは!上長瀬やな和亭(なごみてい)です。🍃
9月に入り、根尾川では落ち鮎のシーズンが本格化してまいりました。当店でも毎日多くのお客様に、極上の鮎料理をご提供させていただいております。この時期になりますと、「やなって全国にどれくらいあるんですか?」というご質問をよくいただきます。
そこで今回は、川漁文化の担い手として30年間この道を歩んできた私たちの視点から、全国の「やな」の現状と、意外に知られていない川漁文化の広がりについてお話しさせていただきます。
やなとは?川漁の原点を知る 🐟
まず、「やな」について初めての方にもわかりやすくご説明いたします。
やなとは、梁漁(やなりょう)を売り物にした食事処で、観光やなとも呼ばれています。川の中に足場を組み、木や竹ですのこ状の台を作った梁(やな)という構造物を設置し、上流から泳いできた魚がかかるのを待つ漁法です。
川の一部をせき止めて導入した水を簀(す)に落とし、簀(す)の上に落ちた魚を捕らえる固定式の川漁の施設で、揖斐川では産卵のための川を下る「落ち鮎」を対象にしています。
当店のある揖斐川町でも、この伝統的な漁法が今も息づいています。設備には木材を骨組みに、竹を籠状に編んだ中に石を入れて川床に固定する「イノコ」と呼ばれるものを使用します。この技術は代々受け継がれてきた職人技で、毎年春先から設置の準備を始め、川の状況を見ながら慎重に組み立てていきます。
私どもの店主も、30年間この川と向き合い続けてきました。川の流れを読み、鮎の動きを予測し、最適な仕掛けを作り上げる。これは単なる漁業ではなく、自然との対話なのです。
実際にお客様に「やな場」を見学していただくと、皆さん驚かれます。「こんなシンプルな仕組みで魚が獲れるんですね!」とよく言われますが、そのシンプルさの中に先人たちの知恵が詰まっているのです。
全国のやなの実態調査 📊
「全国にやなは何カ所あるのか?」この質問に正確にお答えするのは、実は非常に難しいことなのです。
なぜなら、やなは個人経営の小規模な施設が多く、全国的な統計が取られていないからです。また、年によって営業するやなもあれば、休業するやなもあり、流動的な側面があります。
しかし、当店が所属する全国やな協会(仮称)での情報交換や、同業者との交流を通じて得た情報をもとに、おおよその数字をお伝えすることができます。
推定ではありますが、全国には現在も営業している「やな」が 約200~300カ所 存在すると考えられます。これには以下のような施設が含まれます:
観光やな(食事処併設):約150~200カ所
体験型やな(つかみ取り中心):約50~80カ所
伝統的やな(地域の漁業組合運営):約30~50カ所
この数字は、あくまで営業実態のある施設に限ったものです。休業中や廃業した施設を含めると、過去には500カ所以上のやながあったと推定されます。
当店のある岐阜県は、揖斐川、根尾川、坂内川沿いにやなが数多くあり、8月に入ると、あゆ料理を楽しむ人たちで賑わいます。特に揖斐川町だけでも10軒以上のやながあり、全国でも有数の「やな密集地帯」と言えるでしょう。
実際に私たちが他県のやな仲間と交流する中で感じるのは、それぞれの地域に根ざした独特の文化があることです。栃木県の那珂川、神奈川県の相模川、奈良県の吉野川など、清流があるところには必ずと言っていいほど、やな文化が息づいています。
地域別やな文化の特徴 🗾
全国のやな文化を詳しく見ていくと、地域ごとに興味深い特徴があることがわかります。
関東地方のやな文化
関東地方では、栃木県が最も活発です。那珂川では創業88年という老舗の大ヤナもあり、那珂川最大規模を誇っています。関東のやなの特徴は、都市部からのアクセスの良さを活かした観光重視の運営です。
東京からの日帰り客も多く、週末には多くの家族連れで賑わいます。私も何度か栃木のやなを見学させていただきましたが、規模の大きさに驚かされました。当店の3倍近い収容人数を誇る施設もあり、観光バスでの団体客も多く受け入れています。
中部地方のやな文化
私たちの住む岐阜県を含む中部地方は、やな文化の聖地と言っても過言ではありません。長良川水系、木曽川水系の清流に恵まれ、古くからやな漁が盛んでした。
中部地方のやなの特徴は、伝統的な技法を大切にしながらも、味へのこだわりが強いことです。当店でも、魚屋一筋30年の目利きによる厳選された鮎のみを使用しています。岐阜県内のやな仲間と情報交換する際も、必ず話題になるのは「今年の鮎の質はどうか」「どこの川の鮎が美味しいか」といった、品質に関することです。
長良川の支流である板取川には、清流・板取川唯一のヤナ場もあります。このように、一つの川に一軒しかないやなもあり、それぞれが地域の宝として大切に守られています。
関西・近畿地方のやな文化
関西地方では、奈良県の五條市が特に有名です。全国的にもめずらしい「やな漁」を体験できる施設があり、毎年秋に「やな漁」をお楽しみいただけるように仕掛けを設置しています。
関西のやなの特徴は、歴史の古さです。奈良時代から続く漁法を現代に伝える貴重な存在として、文化的価値も高く評価されています。
その他の地域
東北地方や九州地方にも、やなは存在します。ただし、関東・中部・関西ほどの密度はありません。これは、鮎の生息域や川の特性、歴史的経緯などが関係していると考えられます。
興味深いのは、北海道にもアイヌ民族の伝統的な漁法として、やなに似た「テシ」という仕掛けがあったことです。これは現在のやなとは形態が異なりますが、川を遮って魚を獲るという基本的な発想は共通しています。
やな文化が根付く条件とは? 🌿
30年間この業界に身を置いてきた経験から、やな文化が根付き、継続していくための条件について考えてみます。
1. 清流の存在
何より重要なのは、清らかな川の存在です。鮎は水質に非常に敏感な魚で、少しでも汚れた水では生息できません。当店の根尾川も、源流から河口まで美しい水質が保たれているからこそ、美味しい鮎が育ちます。
毎朝、川の状態をチェックするのが私たちの日課です。水の色、流れの速さ、水温など、微細な変化も見逃しません。これらの情報が、その日の鮎の動きを予測する重要な手がかりになります。
2. 地域の理解と協力
やなは単独では成立しません。地域の漁業協同組合、観光協会、行政機関など、多くの関係者の理解と協力が不可欠です。
当店も、揖斐川町の観光協会や地元の皆様に支えられて営業を続けています。地域の祭りやイベントでは、やなの食材を提供したり、やな文化の紹介をしたりと、地域貢献にも努めています。
3. 技術の継承
やなの設置や運営には、代々受け継がれてきた職人技が必要です。川の流れを読む技術、仕掛けを作る技術、鮎を美味しく調理する技術など、すべてが経験に基づく専門知識です。
私たちの店でも、後継者の育成は重要な課題です。単に技術を教えるだけでなく、川への敬意、お客様への感謝の心も含めて、総合的に伝承していかなければなりません。
4. 観光資源としての価値
現代のやなは、単なる漁業施設ではなく、観光資源としての側面が強くなっています。都市部からの観光客にとって、やな体験は非日常的な魅力があります。
当店でも、つかみ取り体験を通じて、都市部の子どもたちが初めて生きた魚に触れる瞬間を数多く見てきました。その驚きと喜びの表情は、私たちにとっても大きな励みになります。
やな文化の現状と課題 💭
全国のやな文化の現状を見ると、決して楽観的とは言えない面もあります。
減少傾向にある理由
- 後継者不足:どの業界でも共通の課題ですが、やな業界も例外ではありません。季節営業であること、天候に左右されることなど、安定経営の難しさが若い世代の参入を阻んでいます。
- 環境の変化:河川改修や上流のダム建設などにより、川の環境が変わり、鮎の遡上数が減少している地域もあります。
- 観光形態の変化:団体旅行から個人旅行へ、宿泊旅行から日帰り旅行へと、観光形態の変化もやな業界に影響を与えています。
生き残りをかけた取り組み
一方で、各地のやなでは様々な工夫を凝らして生き残りを図っています。
当店でも、PayPay対応やSNSでの情報発信など、時代に合わせたサービス改善を続けています。また、地元食材を使った新しいメニューの開発や、体験プログラムの充実にも取り組んでいます。
他のやなとの情報交換では、「農家民宿との連携」「釣り体験とのセット販売」「企業研修での活用」など、様々なアイデアが出されています。
上長瀬やな和亭の取り組み 🏮
私たち上長瀬やな和亭では、やな文化の継承と発展のため、以下のような取り組みを行っています。
品質へのこだわり
魚屋一筋30年の経験を活かし、最高品質の鮎のみを厳選しています。根尾川の清流で育った鮎は、身が締まり、独特の香りと甘みがあります。
毎朝、やな場で獲れた鮎の状態をチェックし、その日最高の状態のものだけをお客様にご提供しています。炭火焼きにこだわるのも、鮎本来の味を最大限に引き出すためです。
おもてなしの心
お客様一人ひとりを大切にし、心のこもったサービスを心がけています。初めてやなを訪れるお客様には、やなの仕組みや鮎の美味しい食べ方を丁寧に説明させていただきます。
特に、お子様連れのお客様には、つかみ取り体験を通じて自然の素晴らしさを感じていただけるよう、安全面にも十分配慮しています。
地域との連携
地元揖斐川町の観光振興にも積極的に協力しています。町のパンフレットやイベントでの鮎料理の提供、修学旅行の受け入れなど、地域の窓口としての役割も果たしています。
情報発信の強化
公式LINE、Instagram、ブログなど、様々な媒体を活用して情報発信を行っています。やな文化の魅力を多くの人に知ってもらうことが、文化継承の第一歩だと考えています。
未来へのやな文化継承 🌱
やな文化を未来に継承していくために、私たちができることを考えてみます。
次世代への技術継承
最も重要なのは、次世代への技術継承です。やなの設置技術、鮎の調理技術、接客技術など、形式知化できない暗黙知の継承が課題です。
当店では、地元の若者や料理を学ぶ学生の研修受け入れも行っています。実際に川に入り、鮎に触れ、お客様と接する中で、やな文化の本質を感じてもらいたいと思います。
新たな価値の創造
伝統を守るだけでなく、新たな価値も創造していく必要があります。健康志向の高まりに対応した鮎料理の提案、SDGsに配慮した運営、インバウンド観光客向けの体験プログラムなど、時代のニーズに合わせた取り組みが重要です。
ネットワークの強化
全国のやな仲間とのネットワークをさらに強化し、互いの知恵を共有していくことも大切です。成功事例の共有、共同でのプロモーション活動、技術研修の相互実施など、協力できることは数多くあります。
まとめ:やな文化の未来への想い 🎋
全国に点在する200~300カ所のやな。これらはただの食事処ではありません。それぞれが地域の自然と人々の暮らしを結ぶ、かけがえのない文化的存在なのです。
私たち上長瀬やな和亭は、これからも根尾川の清流と共に歩み続けます。30年間培ってきた経験と技術を次の世代に伝え、お客様に最高の鮎料理と心温まるひとときをご提供していきます。
9月の落ち鮎シーズンも、まもなく終盤を迎えます。今年の鮎との出会いも、残り少なくなってまいりました。ぜひ、この機会に当店へお越しいただき、やな文化の魅力を存分にお楽しみください。
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

🍃**上長瀬やな 和亭(なごみてい)**🍃
岐阜・根尾川の自然に囲まれた「やな」で、旬の鮎を炭火で。
魚屋一筋30年の目利きが選ぶ、極上の鮎料理をぜひご堪能ください。
📍岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬720
📞 ご予約・お問い合わせ:0585-55-2630
🕒 営業時間: 11:00~ 17:00 ラストオーダー16:30
🚗 大型駐車場完備 / PayPay対応
📲 公式LINE・Instagramで最新情報&お得なクーポン配信中!
👉 LINE:https://line.me/R/ti/p/@792nmhws
👉 Instagram:https://www.instagram.com/nagomitei.yana